去年水俣にやってきて、最初は家探しをしなければならないから、しばらくの間相思社の宿泊棟が我が家だった。職場から徒歩30秒で帰れる、と友達には自慢(?)していた。その際に、胎児性水俣病患者の方の支援にやってきた関根浩さんとしばらく同居させていただいていた。関根さんも私と同じで家探しの仮住まいであった。関根さんは、断食したり、相思社周辺のびわの葉っぱをもぎまくったり、茂道の浜辺ですっぽんぽんで海水浴してきたりするいい感じの人だった。そんな関根さんは、自分の世界を広げてくれた人である。なかなか一人では会いに行けない胎児性患者の方たちとたくさんの接点を作ってくださったのだ。水俣でずっと支援を続けてきた加藤タケ子さんからほっとはうす設立の話を聞いたり、胎児性患者の方たちが小学生に自身の経験を語る「伝えるプログラム」に参加させていただりした。今では、松永幸一郎さんの自宅でご飯をみんなで食べさせていただく。東京生まれ東京育ちの自分が胎児性患者たちの方と食事するなんて思いもしない人生である。だからこそ、その現実をどう受け止めればいいのか、何か役に立てているのか、どうしたいのか自分の立ち位置が掴めない心持ちだった。そんなときに表題の新刊が出たので、読んでみようと思い立てた。
はじめにざっくりとした感想を述べると、本書は胎児性患者の置かれた現況を整理したものとしてとても理解しやすい本だ。そのおかげで、自身の付き合い方を整理しながら振り返ることができた。内容を簡単に説明していきたい。この本の命題は、公害被害を訴えてきた側の「これ以上被害者を生まないようにしよう」という訴えの中に潜む優生思想、これを見つめ直そうというものだ。障害者からすれば、反公害運動の「被害を生まない」とは、障害者がいないような社会を望む、障害者否定の意味が潜んでいる。本書は、これをどう乗り越えるのかを課題としている。
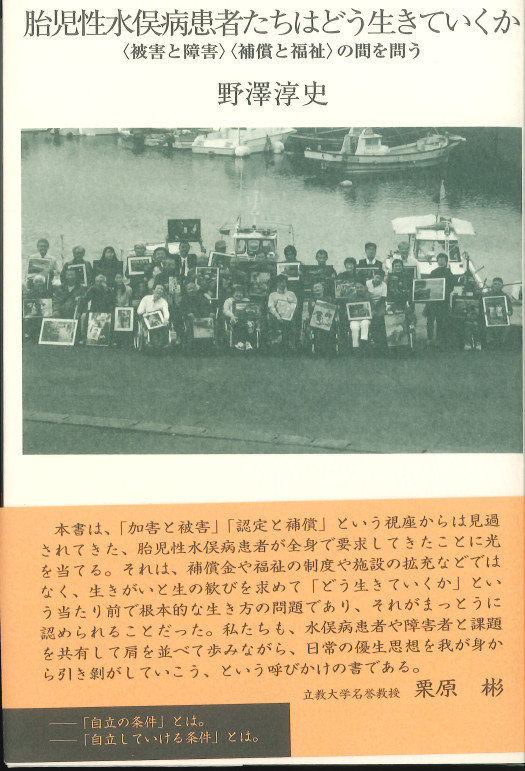
本書の構成は、胎児性患者たちの立ち位置を水俣病問題の経緯や、被害者の視点に立ってきた環境社会学と障害学という枠組みで捉えようとする。障害学は、前提として、問題を回復するのは障害を持つ個人の側ではなく、社会の側であるとして問題を追究していく。障害学のなかでは、障害を二つのモデルで分けている。一つが個人の身体の機能的特質としての障害、もう一つは身体的障害があることで手足が自由に動く人よりも社会の中で劣位な状況に追いやられる障害である。後者の障害をディスアビリティの障害としており、この視点から胎児性患者たちの地域における自立のあり方と補償の問題を整理していく。整理をしている章タイトルをあげていくと、「第3章 胎児性患者たちの自立と支援の変遷」「第4章 水俣病被害補償にみる福祉の系譜」「第5章 補償か、それとも福祉か」になる。このあたりを読んでいると、私が悩んでいた胎児性患者の方たちと付き合い方に対して、まず相手のを知るということが大切だな、と思わされた。
本書の中で自立というのは、「親元でも施設でもない生活を自己決定に基づき送っていくための理念でありまた技法」と定義されている。この言葉を見たら、わずかな時間でも私を諭してくれる加藤タケ子さんの言葉そのものだなと思い返した。今、自分の目の前にある胎児性の方たちの暮らしは、それぞれ想いのある患者、支援者、個人たちの活動の成果として存在しているんだと感じられる。胎児性の方たちが自分の居たい家や場所、しゃべりたい相手、やりたいこと、制限される中で少しでも自身で選択できるように、という配慮が広がっている。けれど、当然その積み重なった歴史はすんなり進んだわけではない。そのような環境を整えてきた「福祉」というプラスイメージの概念にも歴史がある。この本を読むまでは福祉による患者への対応というものはただただ良いものだと思っていたが、1970年代から90年代の患者の認定申請における福祉という言葉は認定制度の枠組みを変えないための免罪符として使われてきていた。近年の患者への福祉対策の拡充は患者たちの要望に応えたものだが、一方で水俣病対策は福祉対策による進展しか見られないのである。また、患者たちが望むのは「福祉ではなく補償を」であるという結論が本書では述べられている。補償には一概に補償金のことだけを指しているわけではないのだ。本書のこの過程と結論は、ぜひ本を手にとっていただいて、患者、支援者の声を読みながら考えてみていただきたい。
そして、最後には「福祉ではなく補償を」という自身の結論をも批判的に捉えながら、福祉へ偏りすぎると加害責任が抜け落ち、補償を強調すれば水俣病以外の障害を持つ人々との分断が生じる、と、「補償も福祉も」というもう一つの結論を導きだしている。そして、本書の課題である私達のなかに潜む「日常の優生思想」をどう乗り越えるか、という問題に向かう。これに対しては、「肩を並べてある共通の仕事に取り組むことで双方がアイデンティティを抜け出す」、という考え方を提示している。この言葉の、アイデンティティを抜け出すという点にとても共感を覚えた。この考え方以外にも、「日常の優生思想」に対する「周辺の考え」、「課題責任」などの有用な考え方、そもそも「日常の優生思想」とは、なども書いてあるので、全部理解するためにはお買い求めください(笑)
自分の患者の人たちとの過ごし方を振り返ってみて、目の前の人を相手にしているときに水俣病患者、というアイデンティティを強く意識し続けることはない。むしろ、何が好きで、何をしたくて、一緒に何をやるか、という相手との当たり前のコミュニケーションをする。確かに介助をすることもあるが、一人の人間として接していれば人間は多面的な生き物でそれぞれに長所短所があるという何も変わらない存在である。個人として深く接することで、他者を多面的に見ることができ表面的、一面的な相手の属性に囚われることはない。今までは、歴史を研究する立場として、紙資料から研究対象の属性がどのようなものかを重視して考える癖が強かったように思う。栗原彬の『存在の現れの政治:水俣病という思想』での結論が、人に対する愛を説いていて、正直研究としてその結論はどうなのともやっとしていたが、水俣に来たら経験知として理解できるようになったかもしれない。個人の良さも悪いところも何でも受け止められるくらいまで共に過ごす、当たり前のことだけど難しいことだ。地域のなかで一人ひとりがミクロな視点で、「被害とは何か」を超えた課題を模索し続けろということだと受け止めて生きていく。
本書の注文はこちらで!


